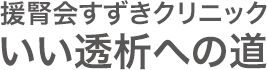郡山で今年初めて雪が積もりました。
昨日より強い寒波がやって来て、この冬一番の冷え込みだそうです。
郡山でも雪が積もっていました。
クリニックでも、ちょっとした雪かきを行いましたが、雪の量も少なく、あまりにも寒いのですぐ終わりにしてしまいました。
今日は雪道で渋滞しているでしょうけれど、雪道はそれほど怖くないですよね。
スタットレスがよく効きます。
一番いやなのは、路面凍結ですよね。
以前勤務していた福島医大病院が山の上に有りましたので、凍った帰り道は最悪でした。
滑って止まらず、怖い思いも何度もしました。
まあ、クリニックと自宅も近いので、路面が心配なときは家でじっとしていればいいだけですので。
これから年末にかけて、少しは暖かくなるようです。
年末にいろいろやることが有りますので、頑張りましょう。
引っ越し終わりました。
最近、私事ばかり書き込んでいますが、引っ越し終わりました。
昨日は、診療後に引っ越しに参加しましたが、全てが済んだのは夜8時過ぎになりました。
何とか寝床を確保しましたが、まだガスも通ってませんでしたので、近くに有る温泉に行ってきました。
今度の住み家は暖かくていいです。
それから、近くに温泉が有ることも気に入っているところです。
昨日も引っ越しが終わってから、夜9時頃、家族みんなで温泉に出かけてきて、ぽかぽかになりました。
これから年末まで、引っ越しの後片付けで忙しそうです。
クリニックの診療も、今年はあとわずか。
最後まで頑張っていきたいと思います。
インフルエンザが流行っている様です。
今年はインフルエンザの流行が早いようです。
特に郡山ではかなり流行っており、今日現在で280人の感染者が出ているとニュースで伝えていました。
かなり流行っておりますので、予防が大切だと思います。
予防としては、
体力をつけて、抵抗力を高めること。
そして、ウイルスに接触するリスクをなるべく少なくすること。
それから、インフルエンザウイルスは湿度に非常に弱いので、加湿器などを使って適度な湿度に保つことなどが大切です。
手洗いは接触による感染を、うがいはのどの乾燥を防ぎます。
家に帰ったら、必ず手洗いとうがいを行うことはとても重要です。
また、外出時はマスクをして、咳やくしゃみの飛沫を防ぐことと共に口の中が乾燥しないような対策を行いましょう。
それから、ワクチンの接種も重要です。
ワクチンは、健康な成人のインフルエンザに対する発症予防効果が70〜90%位有ります。
当院でも、わずかですが10数名分のワクチンが残っています。
他のクリニックでも、もう少し残っているところも有ると思います。
希望される方は、電話でまだワクチンの接種を行っているか確認してから、医療機関を受診してください。
クリスマスはどうお過ごしですか。
本日はクリスマスイブで、明日はいよいよクリスマスですね。
最近の景気の悪さで、なかなかいい話が無い状況ですが、皆さんはどう過ごされますか。
実は、僕は明日引っ越しします。
クリスマス引っ越しとなります。
たまたまそうなったというか、引っ越し屋さんとこちらの都合が合ったのが明日だっただけなのですが、クリスマスも何も無い状態です。
子供のプレゼントも買い忘れて、ほしい商品は売り切れていて無い様で困っています。
今まで住んでいたマンションが、非常に寒く、冬は暖房をつけても厚着をしなければいられないほどだったので、冬を迎える前に思いつきの様な感じで引っ越しを決めてしまいました。
今度のお部屋は寒くないと言うことで決めました。
まあ、クリスマスとお正月は、家でゆっくり過ごそうと考えています。
このブログを見ている皆さんが、よいクリスマスとお正月を迎えられるように願っています。
白鳥飛来
今日、クリニックのそばを流れる逢瀬川沿いを散歩していたところ、通りがけのおばさんから白鳥が来ていると教えてもらい、子供たちと見に行きました。
別の川沿いにすむおじさんは、逢瀬川のこのあたりに来るのは初めてだと話していました。
僕の実家がある町も、以前から白鳥飛来地として知られていますが、鳥インフルエンザの問題があって、今年から餌付けが廃止されています。
毎年、お正月に実家に帰ったとき、子供たちを連れて見に行くのですが、餌付けを行わなくなったので、今度のお正月はあまりいないかもしれません。
もしかしたら、そのような影響があり逢瀬川にやって来たのかのかもしれませんね。
今年も、後一週間ちょっとです。
『終わりよければ全てよし』とも言いますので、頑張っていきましょう。
プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。