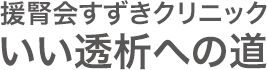消火訓練が有りました。
月曜日に消火訓練を行いました。
防災の日は9月1日だし、なんでこの時期なのかと思いつつ、スタッフに言われるがまま、消火訓練を行いました。
雨が降っていましたので、クリニック玄関での開催となりました。
まずは指導してくれる業者さんから説明がありました。
たまたま来院していたメーカーさんにも参加してもらいました。
消火器は上に向けては駄目だそうです。
院長が上に向けて放水したところ、左から待ったの手が出ています。
きちんと地面に向けて放水して、本日の消火訓練は終了となりました。
院長が漫画になりました。
先日参加した透析学会の最終日に、ネット上で交流のある先生や透析者の皆さんとランチをしました。
僕のとなりは、『透析バンザイ』というブログを書いているバンザイさんでした。
ブログには、バンザイさんが他の透析者の方や医師・スタッフとのふれ合いを通じて感じたことを表現した漫画が書かれています。
このブログは本にもなっています。

そのバンザイさんが、今回の食事会の事と、震災直後の当院の事を漫画にしてくれました。
http://blogs.yahoo.co.jp/bannbann0821/25895756.html
書かれた内容は、ランチの時にお話したことですが、本当に僕が経験したことがリアルに書かれていて驚きました。
ちなみに、次の日というのは、土曜日に片付けと電源の復旧作業をしたので、その次の日曜日からです。
今回の震災は、とても大変な災害でした。
にもかかわらず、日曜日から透析を行うことが出来、しかもその後も中断せずに行えたのは、とても幸せなことです。
スタッフ及び関係者に感謝したいです。
充実した日曜日
今日は小雨がふる日曜日でしたが、1日中忙しく充実した1日でした。
子供が通う幼稚園が、キリスト教の幼稚園で日曜日に礼拝が有ります。
我が家は特にキリスト教ではないのですが、本日は父の日礼拝だというので朝から出かけてきました。
初参加でした。
教会でお祈りをして、牧師さんの話を聞き、幼稚園に戻ってお歌を歌い、父兄の自己紹介なんてやっていました。
隣のお父さんが避難の方で、自己紹介の時に涙ぐんでいて少しもらい泣きしてました。
その後、立教大学のお兄さん達が演劇をしてくれて次男と共に楽しい時間が過ごせました。
お昼は、トクちゃんラーメンに行ってきました。
最近、グルメネタが少ないと方々から言われていますので、是非とも写真を撮ってこようと思い、
塩ラーメン撮影してきました。
醤油ラーメンが美味しいお店ですが、塩ラーメンのスープもとても美味しかったですよ。
そして、午後からは子供たちと郡山テアトルへ。
「ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦」
歴代ヒーローがたくさん出てきて懐かしかったですが、ストーリーはしょぼい感じでした。
仮面ライダーの方がドラマとしては面白いかな。
帰りは、ママが迎えに来てくれる間に珈琲館でちょっと一息。
子連れは気を使わなくていいお外がいいと思い、お外の席にしました。
座ってから、そういえば放射線気にしなかったと思いましたが、まあ少しぐらいはいいでしょうと思いまして、そのままお外でティータイムとしました。
珈琲館のマスターが町中はコンクリートが多いから、0.4マイクロシーベルトぐらいで大丈夫だよと言っていました。
その後は、いつもの日帰り温泉。
これも4月頃から子供たちと露天風呂に入っていて、妻に言ったら驚かれたくらいです。
今日は充実した日曜日でした。
明日からまた頑張ろう。
木曜日の看護学校の講義スライドがまだなので、これから夜なべして作ります。
飲み物や食品の暫定基準値
みんなの党の柿沢未途議員が内部被曝について国会で質問したとツイッターで発信していました。
福島第一原発から北西方向の広範囲でチェルノブイリを上回るようなセシウムの土壌汚染が観測されている。セシウムを吸収した農作物や畜産品を通じた内部被曝をどう避けるかが重要な課題。
しかるに日本の暫定規制値は、飲料水や牛乳等の飲み物は200Bq、野菜等の食べ物は500Bq、それだけ。しかも規制値があまりにも高すぎる。早急に見直しが必要だ。大塚副大臣「今の基準はICRP等の科学的知見に基づき決定し、所管の諮問機関が現状ではやむを得ないものとして是認したもの。」
と有りました。
高すぎるとあったので、調べてみました。

セシウムの基準値は、IAEAや消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年にFAO及びWHOにより設置された国際的な政府間機関であるコーデックス委員会の規制値より低いです。

WHOやEUの規制値よりも低いようです。
1986年11月に決まった輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は、134Csおよび137Csの濃度として370Bq/kg以下ですので、野菜、穀物の500Bq/kg以下はそれほど変わらない様です。
しかし、柿沢未途議員が規制値があまりにも高すぎると言っていて、大塚副大臣もやむを得ないものと言っているので、やはり高すぎるのでしょうか。
幼児を持つ親としては、出来るだけ安全域にあるようにしてもらいたいと考えています。
そろそろ落ち着いてきているので、高すぎる数値はやめて欲しいです。
- 2011.06.21
- 生活 / くらし
今、空間の放射線量は
レントゲン撮影を行っている医師や看護師は、放射線従事者として一ヶ月間の外部被爆線量を測定しています。
当院でももちろん行っておりますが、今回業者さんにお願いし、5月一ヶ月間の放射線量をいくつかの場所で測定しました。
クリニック外壁、マンション室内2階と8階です。
最近結果が届きましたので、ここに示します。
1ヶ月の積算量は
クリニック外壁は0.64mSV
マンション室内2階 0.17mSV
マンション室内8階 0.15mSV
0.17mSVは、換算すると0.2μSV/時です。
郡山でも我が家の周辺はかなり数値が高いのですが、マンション室内ですと0.2μSV/時くらいでしたので、妥当なところみたいです。
今回、昨年秋から冬にかけてのコントロールの結果も知る事が出来ました。
コントロールは、自然にある放射線量を記録しています。
9月 0.16mSV
10月 0.16mSV
11月 0.12mSV
12月 0.16mSV
1月 0.12mSV
でした。
http://eneco.jaero.or.jp/important/radiation/radiation04.html
このページによると、福島の自然放射線量は1.04ミリシーベルトとなっており、10月から1月までの合計×3=1.68ミリシーベルトとなり、福島県の数値より高くなりますが、地域によってはこのくらいの数値になる事を考えれば、コントロールも妥当だと考えます。
つまり、原発事故前の放射線量とあまり変わらなくなったと考えていいようです。
コンクリートの上で生活していれば、現在の空間の放射線量はほぼ無視していいかもしれません。
そのため、現在最も心配すべきことは、現在福島で栽培されている米や野菜からの内部被爆であると考えます。
作物が出回ってしまえば分かりません。
さらには、現在子供たちには公園で遊ぶことをやめさせていますが、この様な環境が続くことは望ましくないので、学校だけでなく公園でも表土を削るなどの対応をして欲しいです。
これは、現地の親の願いです。
プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。