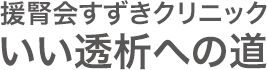慢性前立腺炎と体外衝撃波
英国の泌尿器科雑誌に、体外衝撃波が慢性前立腺炎に有効だったという報告が有りました。
慢性前立腺炎はやっかいな病気です。
会陰部や下腹部,陰嚢部などに鈍痛や不快感を感じ、頻尿,排尿痛,残尿感などもみられます。射精前後に痛みなどもよくある症状です。
慢性的に症状を訴え、直らないで困っている患者さんが沢山いらっしゃいます。
慢性前立腺炎の診断は、診察の時におしりから指を入れて前立腺をマッサージし、痛みを感じるかどうかで判断します。
慢性前立腺炎には、細菌性前立腺炎と非細菌性前立腺炎があり、細菌性前立腺炎は、前立腺マッサージを行い、膿が出てきたときに診断されます。
膿が出てこなければ非細菌性前立腺炎となります。
一番直りにくいのが非細菌性前立腺炎であり、前立腺痛とか前立腺症と言う名前でも言われます。
ずっと座っていることや、冷え、ストレスなどが原因となるようで、30−40歳代に多い病気です。
治療は、抗生物質の投与や前立腺炎に適応のあるセルニルトンというお薬を処方しています。
改善しない場合、α1ブロッカーという薬を追加する場合が有ります。
しかし、それでも直らない患者さんがかなり沢山いることが、前立腺炎の一番困ったところです。
当院では、数名ですが、光治療を行うことで劇的に改善している患者さんもいらっしゃいます。
これは、前立腺に向かう神経を刺激して、前立腺周辺の血行を改善する効果があります。
多分、体外衝撃波も神経を刺激して血行をよくするのではないかと思いますので、通じるものがありそうです。
温泉卵やってみました。
昨日お昼に、透析スタッフみんなが温泉卵をつぶしてみました。
みんなの話からは、『かなり強く押しても割れなかった』と言うのが感想の様です。
僕もやってみました。。
時々止血をするのですが、いつもよりは強めの感覚でした。
ただ、押すのだけれど、卵が割れない様に押すという感覚はあるように感じました。
患者さんの止血を行うときの感覚に似ているかもしれないと少し感じましたね。
それで、『かなり強く押しても割れなかった』ことについてのみんなの感想は、皇室も泊まったことがある月岡ホテルの温泉卵は、普通の卵を使った温泉卵よりも殻が厚くて、しっかりしているので割れなかったのではないかと言うことでした。
割った後、すごく美味しかったです。
次回は、スーパーで売っている一般的な温泉卵で試してみたいと思います。
透析液清浄化報告10月号
今月の当院で使用している透析液のエンドトキシン濃度及び、最近培養検査の結果が出ました。
ET活性値:0.3 EU/L未満 (測定感度未満)
生菌数:0.1 CFU/mL未満(測定感度未満)
でした。
日本臨床工学技士会の出している透析液清浄化ガイドラインには、
透析用水生物学的汚染管理基準
ET活性値:50 EU/L未満 目標値 1 EU/L未満
生菌数:100 CFU/mL未満 目標値 10 CFU/mL未満
測定頻度:月1回以上測定
とあります。
当院では、日本ポール 37mmクオリティモニターとR2A培地の2種類の細菌培養測定装置を使っています。
エンドトキシンは日機装社製のトキシノメーターです。
おみやげは温泉卵
昨日の記事で、研究会でいろいろためになる話を聞いてきたと書きましたが、その中で特に役立てそうな講演がありましたので、記事にします。
透析にはシャント血管に針を刺す操作が必要です。
針を抜いた後は出血しますので、必ずガーゼなどを使って出血部位を押さえなくてはいけません。
透析室には、たくさんのスタッフがおり、若い人から、年を取った人。性別も違います。
本来は止血操作も同じ強さとしなければいけないのですが、なかなか同じ強さで圧迫するのは難しいのではないかと思います。
これまでは新人のスタッフに対しては、このぐらいと口で止血の強さを伝えていました。
圧迫は、強すぎてはシャントがつぶれてしまいます。
出血しないぎりぎりの強さで押さえることがポイントです。
そのぎりぎりの強さが、温泉卵を押して割れないくらいの強さだそうです。
この講演を聞いて、思わずこの方法についていくつか質問してしまいました。
一つは生卵やゆで卵ではだめかについてですが、やはり温泉卵でなければならないそうです。
研究会が行われたホテルからスタッフへのおみやげとして買ってきた温泉卵と、学会スタッフの方が僕が質問してる写真を撮ってくださって、写真をいただきましたので、並べて撮影しました。
今日、早速みんなでこの温泉卵を押してみたいと思います。
アクセス研究会
今週の25、26日と山形県かみのやま温泉で、透析で使用するシャントの研究会が行われました。
全国的な研究会でしたので、土曜日の外来後に参加させていただきました。
いろいろと勉強しましたので、これからの臨床に役立てていきたいと考えております。
帰りの新幹線で撮影した、かみのやま温泉駅の写真です。
以前、山形で行われた東北腎不全研究会も土曜日の午後から行われ、お昼を食べる時間がなく新幹線に飛び乗ったのですが、今回も同様にぎりぎり間に合った状態でした。
その時は、米沢まで我慢できず、途中で「はらくっち弁当」を食べてしまったことを書きましたが、今回は米沢名物「牛肉ど真ん中弁当」を是非とも食べたいと思い、米沢駅まで我慢しました。
米沢に着いたのが、2時半ですので、お腹はペコペコでした。
米沢駅につく前に、販売員のお姉さんに「牛肉ど真ん中弁当」を予約して準備万全のはずでした。
ところが、いくら待っても弁当が来ないのです。
実は、お弁当が積み込まれたのは、僕が乗っていた車両から一番遠い車両で、かみのやま温泉手前ぎりぎりでお姉さんが到着したので、車内で食べられず、予約をキャンセルするしかありませんでした。
どうも、僕は「牛肉ど真ん中弁当」と相性が悪いようです。
でも、是非とも食べたいと思っていますので、この次も機会が有ったら狙っていきたいです。
プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。