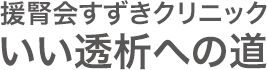休日当番医
本日は、休日当番医です。
休日当番医は、小児科系、内科系、その他の3つの医療機関が当番医として診療を行います。
当院は、今回は泌尿器科として診療を行っていますが、午前中来院された方は、内科2:泌尿器科1の割合で、内科の患者さんでも、ほとんどの方が風邪や胃腸炎の方でした。
午前中はかなり混雑しましたが、午後からはそれほど混雑せず、のんびりとした診療になりました。
風邪の患者さんが多いと言っても、中には実は重症の疾患が隠れている場合もあります。
ただの咽頭炎と思っていても、扁桃周囲膿瘍や喉頭蓋炎などの入院を必要として命にかかわる疾患が有ります。
必要な方には、症状がまだ出始めの段階で、これから悪くなることがあることを説明し、悪くなった場合には必ず医療機関を受診するようお話ししました。
薬が有るからと言って安心して我慢してしまう方もいますので、状態が変わったときのことをしっかり説明する必要が有ります。
もうちょっとで休日診療も終わりになります。
明日、明後日はお休みなので、ちょっと楽しみです。
1月1日今日はお休みです。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今日は、クリニックがお休みで、デパートの初売りに行ったり、年賀状の返事を書いたり、ゆっくりしていました。
当院は、透析をメインとしたクリニックです。
一般的に透析は週3回行っておりますので、月水金もしくは火木土に患者さんは来院します。
と言うことで、月火水木金土は透析が有り、お休みは日曜だけのはずなのですが、開院以来、火木土の透析が開始していませんでした。
いよいよ1月6日より火木土の透析が始まります。
そのため、1月は、今日と3日はお休みとなります。
でも、5日からは、日曜以外は毎日お仕事となります。
まあ、好きな仕事をしているので、全然苦にはなりませんが、家族には迷惑をかけております。
しかも、明日の2日は休日診療が有り、透析診療と合わせ、職員総出でお仕事です。
今年も1年頑張りたいと思います。
宜しくお願いいたします。
良いお年を!
今年も残り1時間くらいになりました。
大学を卒業して、泌尿器科医になってからずっと透析診療に従事してきました。
血液透析も管理していましたが、大学では腹膜透析や腎移植を中心に診療をやっていました。
最近では、太田西ノ内病院でバスキュラーアクセスを中心に透析診療に関わっておりました。
数年前にオンラインHDFを知り、そして透析は時間を延ばしたり、効率を上げることで予後が変わることを知りました。
実際に、通常の透析の10年生存率が60%くらいで有ることに比べ、オンラインHDFで効率を上げた透析をしている施設では90%以上有ることが報告されています。
そのような治療を、自分の思ったようにやってみたいという気持ちが強くなり、今年の5月にクリニックを開院しました。
なかなか理想の透析治療を行うにはほど遠いのですが、スタッフと共に来年も頑張っていきたいと考えています。
どうもありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
焼オヤジ
先日、ネットで郡山のラーメンを調べていたところ、焼オヤジという店が引っかかり、気になったので行ってきました。
11時から営業でしたので、その直後に入店しましたところ、他のお客さんはおらず、家族みんなで座敷に座り、ラーメンを頼みました。
一般的な中華そばで美味しく、チャーシューが特に美味しかったです。
そぼろご飯も付けて、子供たちといただきました。
でも、後から入ってくるお客さんは皆さん定食を食べていて、すごく美味しそうでした。
やっぱり鉄板焼のお店ですから、ラーメンでなく定食だったのかもと反省しながら帰宅しました。
それで、今日のお昼リベンジに行ってきました。
僕は、デミグラスソースのメンチカツ定食を食べ、嫁さんは若鶏の照り焼きを食べました。
定食はいろいろなおかずが付いていて、楽しめます。
メニューはメンチと書いてあったのですが、実際には柔らかいハンバーグでした。
軟骨も少し入っていてとても美味しいハンバーグでした。
照り焼きも美味しく、鉄板に乗っており熱々でした。
食べ出したら、子供たちの食い付きが予想以上に強く、ハンバーグの4分の3は取られてしまったので、そばに付いていた温泉卵の卵ご飯となってしまいました。
もうちょっとお肉が食べたかった。。。
でも、美味しかったです。
今日から外来はお休みです。
引っ越しの後片付けがなかなか進みません。
出てくるものはゴミばかり。
マックOSは現在10.5ですが、大切にしまっていたOS9のソフトがたくさん。
使わないですけど、結構高かったんだと思ってしまう自分がいます。
勇気を持って捨てました。
電源コードや、LANなどがわんさかあります。
今使っているものの一部かもしれないというと捨てられないのですが、ほとんどは捨ててしまった機器の付属品のようです。
日曜日にやっと年賀状を探し当て、印刷して出すことが出来ました。
段ボールが多すぎて、発掘が大変でした。
今日から外来診療はお休みです。
でも、透析診療はいつも通りに休まず行っています。
5月12日に開院してから、たくさんの患者さんに来院いただき、ありがとうございました。
来年も、引き続きよろしくお願いいたします。
プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。