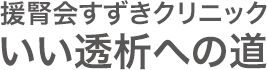震災における対応課題4

事前に離脱方法を統一化していませんでしたので、スタッフによって離脱させた患者数に差がでてしまいました。
そこで、皆で話し合い、切断法にて統一することといたしました。
ただ、これは今回の様に電源が喪失するほどの大惨事の場合です。
4月11日に起こった震度5の最大余震時にも透析を行っていましたが、このときはすぐに回収を行い終了することが出来ました。
切断という方法は、通常行う方法で無く緊急時に出来ないのではと言うことを言われます。
ただ、鉗子をかけて接続部を外す方法だと、その後避難している間、鉗子をかけた部分が外れても分からない可能性があります。
また、セイフティー針にロックをかけて回路から外す方法は、長い揺れが続いた後では指が震えてしまった経験から、ひどい揺れに耐えた後に細かい操作を行うこと難しいと思います。
これらのことから、鉗子をかけてその遠位を切断し、患者さんに鉗子を持って逃げてもらう方法が一番早く安全と我々は考えています。

震災における対応課題3

震災後の対策です。
RO装置は、ゲルセーフにて固定していたものの、45cm移動し、漏水検知も切断されてしまいました。
その後の最大余震でもさらに動いて、後ろのチューブが伸びきってしまいましたので、その後すぐに元の位置に戻しました。
今後は、床に直接固定する工事を行う予定です。

落下した検査機器は壁際に寄せて設置しました。
これらは高額な機械ですので、さらに転倒防止のシートやベルトを用いた対策を行う予定です。
震災直後、血液ガス分析装置が転落して画面がくしゃっとなってしまいました。
高額な機械ですので大変だという事もありましたが、検査会社へ検体の輸送が出来なくなった状態でさらに出来る検査が少なくなってしまったと言うことは反省すべきことでした。

鉗子の位置は、生食と一緒にかけていた為に地震の揺れで散乱してしまいました。
そこで、コンソール脇にマグネットフックつけて、鉗子が飛んでしまわない工夫をいたしました。
震災における対応課題2
続きです。

今回の震災で、ゲルセーフで固定してあった重さ1トンのRO装置は脚の部分がちぎれて動いてしまいました。
AB溶解装置もゲルセーフで固定してありましたが、同様に動いてしまいました。
機械室の卓上に有った浸透圧計、血液ガス分析装置、パソコンは無惨に落下してしまいました。
透析フロアでは、ベッドが大きく動きました。

10名が透析中でしたが、大きな揺れによるベットからの転落や透析の穿刺針が抜けてしまうと言う事は有りませんでした。
ただ、あまりに揺れたため、透析装置のフック部分にかけてあった鉗子がほとんど吹き飛んでしまい、緊急離脱を行うためにスタッフは先ず鉗子を探す事から始めました。
揺れもひどかったですが、エアコンの蓋が取れ落ちてきて、壁に多数の亀裂が入り、そのため砂埃が舞う状況でした。
もちろん電源が破壊され、非常用電灯のみの状態でした。
倒れた冷蔵庫のファンがカンカンカンと大きな音を鳴らしていました。
我々は、患者さんを退避することを最優先としました。
そのため回収をせず、緊急離脱としました。
事前に離脱法を統一していなかったため、7名が鉗子をかけてロック部分を外し離脱。2名が鉗子をかけた後ラインをスタッフが切断して離脱。
オーバーテーブル上に止血バンドとガーゼが置いてあった1名だけは抜針後止血バンドで止血して離脱しました。
後日、構造計算を行う一級建築士にクリニックの柱が大丈夫であるか確認してもらい、全く問題がないことを確認しています。
当院は、鉄骨2階立てですので、地震には強いのですが揺れは強いようで、震災時はとても怖かったです。
『震災における対応課題』
土曜日に郡山市で行われた福島腎不全研究会で当院臨床工学士の入谷麻祐子が、『震災における対応課題』について発表いたしました。
発表スライドは、クリニックホームページの学会発表にpdfファイルとして掲示しましたが、ブログでも紹介したいと思います。
https://enjinkai.com/society/index.html

表題のスライドです。

当院では透析室の地震対策として、次のスライドに示しますが、免震装置と地震感知機能を採用しています。
今回の東日本大震災を経験して、これらの対策が有効であったか、震災時の対応と今後の対策をどうすべきか検討しました。

震災時の対応として、透析機械室では、RO装置はゲルセーフと言う転倒防止器具の上に設置してありました。
ゲルセーフは、衝撃や振動を90%以上吸収し、弾力性と粘着性に優れているため、あらゆる揺れに耐えられると言われていました。

多人数用透析液供給装置は、免震装置上に設置してあり、配管はフレキシブルなチューブ配管を使用していました。

透析室では、コンソールに地震検知システム搭載を採用していました。これは、福島県内では初めてだったようです。
さらに、コンソールのキャスターはフリーロックとしていました。
パート医療事務職員を募集します。

援腎会すずきクリニックでは、業務拡張に伴い、医療事務(パート)を募集いたします。
詳細はホームページのスタッフ募集をご覧ください。
https://enjinkai.com/recruit/index.html
募集職種 パート医療事務
応募資格 医療事務
経理の経験がある方、ワード・エクセルが使える方大歓迎です。
勤務時間
月〜土/9:00 から 12:30
週のうち4・5日の勤務です。
休日 日曜・祝祭日
選考方法
書類審査および面接。
自筆の履歴書( 写真付き) をご郵送願います。
履歴書の返却はいたしません。
応募先一度お電話でご連絡ください。
その後、履歴書を郵送願います。TEL:024-925-0860
プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。